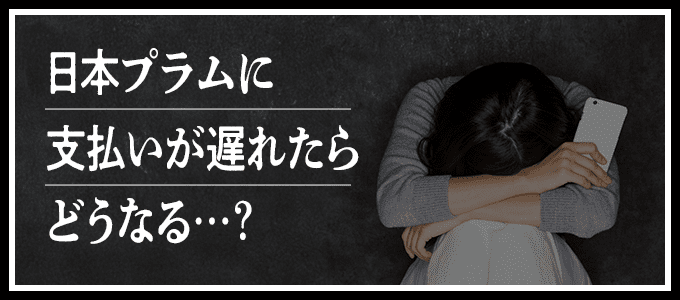

口座引落不能・郵送による支払い案内
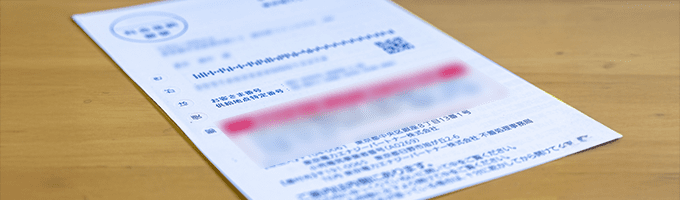
支払日(毎月5日)の自動引落しが残高不足などでできなかった場合、支払予定日から約3~5日後に日本プラムから郵送でコンビニ払い用のハガキ(請求書・支払用紙)が送付されます。

初回の引落し不能時点では延滞利息も日割りで発生しますが、請求書の金額には催告手数料(督促事務手数料)やコンビニ収納手数料が含まれるため、元の引落予定額より高くなります。
このハガキに記載の支払期限までに、記載のコンビニ払込用紙を使って支払う必要があります。

電話督促や督促状の送付
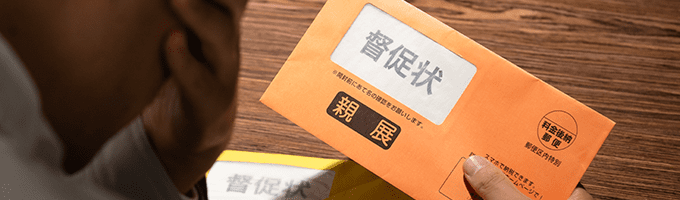
最初の通知書の支払期限までに入金が確認できない場合、一定期間後に再度ハガキや手紙による督促状(コンビニ払い用紙付き)が送付されます。
内容は初回と同様ですが、延滞が続いた日数分の遅延損害金(延滞利息)が追加された金額が請求されます。
併せて日本プラムのカスタマセンターから電話での督促連絡も行われます。

督促の電話では支払いの意思確認や入金予定日のヒアリングが行われ、できるだけ早期の支払いを促されます。
なお、最初の支払期限を過ぎてから自主的に銀行振込で支払いたい場合は、延滞利息を含めた正確な金額を事前にカスタマセンターに確認する必要があります。

延滞時の利息や追加費用

延滞すると通常の支払額に加え各種手数料が発生し、経済的負担が増します。
まず、遅延損害金(延滞利息)は年率20%に設定されており、支払日翌日から入金日までの日数分が滞納元本に対して日割計算されます。
例えば10万円の支払いを30日間延滞した場合、約1,643円の遅延利息が加算されます(10万円×20%÷365日×30日)。
この遅延利息に加え、督促状発行にかかる事務手数料やコンビニ収納手数料が請求額に上乗せされます。

もしどうしても支払いが難しい事情がある場合は、放置せず早めに日本プラムのカスタマセンターに相談しましょう。
相談することで支払猶予や分割見直しなど何らかの解決策が提示される可能性があります。
日本プラム側も「支払いが難しい場合はお早めにご相談ください」と案内しています。
延滞の放置は状況を悪化させる一方なので、誠意をもって連絡し、解決に向けた対応をとることが大切です。
ローンの利用にあたっては、契約内容をよく確認し計画的に返済することが何より重要です。
不明点があれば日本プラムの窓口で問い合わせるなど、慎重に対応してください。
長期延滞時の措置(契約解除・一括請求・法的措置)

再三の督促にも応じず延滞が長期間(おおむね2~3ヶ月以上)継続した場合、ローン契約上の「期限の利益」を喪失する事態となります。
期限の利益の喪失とは、当初約束した分割払いの権利が取り消され、残債全額を一括で直ちに返済しなければならなくなることを意味します。
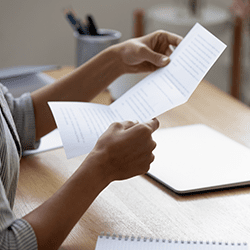
日本プラムから内容証明郵便などで契約解除と残額一括請求の通知が届き、以降は分割払いではなく残債全ての支払いを求められます。
これにも応じない場合、法的措置に移行します。
具体的には債権回収のための民事訴訟の提起や、判決取得後の強制執行(給与や預金、不動産など財産の差押え)といった措置がとられる可能性があります。

なお、日本プラムは貸金業法及び割賦販売法に基づき、延滞情報を信用情報機関(CIC等)に登録する義務があります。
おおよそ3ヶ月分の支払いが滞るとCICに延滞情報が登録され、完済後5年間はその情報が残存します。
延滞情報が載ると日本プラム以外の金融機関・クレジット会社からの新たな借入やクレジットカード利用が制限されたり、既存カードが利用停止・限度額減額されることもあります。
